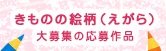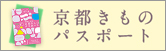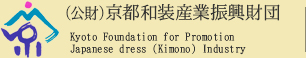きものを知る
第七回 きものの世界っておもしろい

株式会社越村染工場 3代目 越村 一也氏
京都市中京区大宮通御池上る 株式会社越村染工場 3代目。
1964年生まれ、代々続いた染工場に生まれ学卒後は室町の前売問屋で6年間の修行。家業に戻ってさらに9年の経験を積み上げる。「誂え」と呼ばれる友禅の受注生産からきもののメンテナンスまで、幅広く対応するための努力は惜しまない。京都誂友禅青経クラブ平成15年度会長、「関大亭一八」というアマチュア落語家の顔も併せ持つアクティブ派。軽妙な語り口調が商売にも生かされている。
http://www.shikkaiya.jp/
悉皆屋の心得は
京都市中京区、二条城にほど近い場所に越村染工場はある。そのむかし、洗い作業が行われていた堀川を臨むこの地域には染屋さんがとても多かった。そんな中で、越村染工場はひっきりなしに人が出入りする悉皆業を営んでいる。「悉皆屋」という言葉、また業態自体、地元でもその意味を知らず首を傾げる人は多いだろう。
「一言で言えば加工の請負業です。一般には地方の小売店などからシミ抜きや染め替えの仕事をもらってきて、京都の各工場へ出す業種です。これは組合で言うと「京染卸」がそれに当たります。また我々のような仕事も悉皆という呼び方をします。近年では『染匠』とも言います。つまりは京友禅を制作するにあたりお客様の意向を組み取り、最も適した職人さんを選び加工や制作に対しての指示を出すという役割を担う職種です。染めの工程は大変複雑。途中でトラブルがあればそれらに対応したり、進行整理をしたりと、そう、プロデューサーと言ったところですね。
オーダーメイドの友禅きものを作りたい、と思ったお客さんはまずは小売屋さんに相談する。それを京染卸が請け、私たちのような工場に発注するというわけです。この流れはむかしから変わりません。」と越村さん。
最近は白生地からの誂え(オーダーメード)が増える傾向にあるとのこと。直接お客様からニーズを伺わない分だけ、いかに希望どおりの製品を仕上げることができるかは越村さんの腕に掛っている。やり直しや修正が多ければむろんコストも発生するだろう。どんな知識が必要なのか、また資質あってのものなのだろうかと尋ねてみた。
「浅く広い知識、新しい技術に関する情報収集や勉強、あとは経験、実績も手伝っての『消費者のセンスを読み取る勘』みたいなものでしょうか?」この分野に求められるスキルも、他の様々なものとやはり共通すると実感。
きもののメンテナンス(クリニック)部門にも力を注いで
越村さんのところでは、小売屋や、それを経て京染卸に持ち込まれる様々なトラブルきものの手入れも請けている。「他所ではこれは無理だと言われた」というシロモノまで対処に努めるというから凄い。
「刺繍が外れたり、カビが生えたりシミが付着したり、色スジがついてしまったりといろいろですね。「要見積」が入荷全体の一割ぐらいあります。せいぜいその場で返事するようにしています。時として講演会の要請を受け、『きもののお手入れについて』などの演題で話すこともあります。本当は染め替えや彩色直しなどの上級テクニックを紹介したいのですが、質問を受け始めると『保管の方法』や『脱いだ後の始末』だけでかなりの時間を要します。でもみなさん、それが詳しく知りたいのですよね。アドバイスと言うなら、『年に一度は虫干しをしましょう』ということでしょうか。」
熟練の技を持つ職人を抱える強みが、引き合いがあった仕事は断らないという強い姿勢に繋がっている。『職人人材バンク』と言っても過言ではないだろう。そんな越村さんが心配するのは未来に向けた職人さんの育成。少しでも業界に対しての理解を深めてほしいという気持ちが、オリジナルサイトの立ち上げ意欲に拍車を掛けた。1年がかりで取り組み、今年の9月10日にプレビューアップしたばかりのそのサイトは、わかりやすい内容とまとまりの良い美しいデザインで好評を博している。「頻繁に更新していきますよ。ええ、もちろん自分の手でやります!」、と大いなる意気込みを見せてくれた。
探究心を忘れずに
きもののマーケットの新しいカテゴリについても、越村さんは積極姿勢で模索を続ける。
その視点にはなるほどと思わせるものがある。
きもの自体、家業にあって生まれたときからずっと身近な存在だった。落語の高座に上がる時、またプライベートな集まりにも自信を持って着る。そして、年柄年中たくさんのきものが越村さんの前を通り抜けていく。とても自然である分、本来は既成概念や視野にとらわれて当たり前なのかもしれない。
でも越村さんは違う。広く張るアンテナ、突き詰める執着心、どちらが欠けてもプロデューサー業が成り立たないことを良く知っている。
得意の落語を生かし、今後、業界理解に向けての広報活動にもきっと寄与されることだろう。
ぜひ、その匠の域にも触れてみたい。