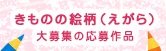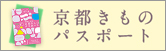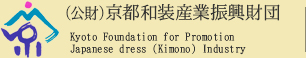きものを知る
第四回 きものの世界っておもしろい

吉川染匠株式会社4代目 吉川 博也氏
京都市上京区千本通下立売東入ル 吉川染匠株式会社4代目。35歳。
18歳で家業の染匠を継承すべく同業他社へ入社。10年間の修業を経てのれん分けを受け独立。さらなる成長に期待が寄せられる若手染匠として敏腕を振るう傍ら、京都染織青年団体協議会の要職にも就く。
野球選手になりたかったと、幼きころの夢を語る氏はスピード感と若々しい判断力を備え持つ。業界の若手リーダー的存在と人望厚し。
「染匠」の心を今に引き継ぐ -染匠の一日密着レポート(その3)-
吉川さんのセンスから想像すると、シャープでモダンな絵柄を好むのではないかと思っていた。「いや、違います。逆に反対のタイプをきものには求めます。古典柄を生かした華やかではんなりしたものが好きですよ。例えばこの萩の絵柄もそう。デフォルメせず忠実に本物の美しさを表現してもらってます」。
繊細な筆の先に広がる花々の存在感。古典的でありながらなぜか新しさも感じる。「どんな人がこれを着るのだろう」と、思わず羨望のため息が出てしまう。
美しいものはいつの世も人の心をときめかせる。次に訪れた挿友禅職人さんはバラの絵柄に取り組んでいた。元来、きものの柄にバラを使うことは珍しく、豊かな創造力と感性が必要とされる難しい素材ではないだろうか。鮮やかな地色の上、片刀刷毛を使った細かい色挿し作業が行われている。「普通使うものは彩色筆か丸刷毛、片刀刷毛をこれだけ器用に使いこなせる職人さんはなかなかいないのですよ。彼はまだ25歳、持って生まれた才能なのかもしれません。将来有望株と言われている青年ですよ」と。優しい笑顔の吉川さんに、若手職人を育てる自負を見る。技術を伝承する若手の育成は業界にとっても大きな課題、様々な要因から成り手が少ない技術者の確保には苦労があるに違いない。縁あって、吉川さんが育てて行こうと決めたこのバラを染める青年は、スノボやサーフィンについても彼を師事すると聞いた。自分を表現することができ、さらには高めていける技術を身に付けることは素晴らしい。惑うことの多い今の日本社会、生きる道を模索する若者たちにこのような仕事・業界があることを知ってほしい。
最後に伺ったのは下絵屋さん。この分野では大御所のこだわり職人さんらしい。今日は、生地に下絵を描く前の考案段階に使う草案(ラフデザイン)をもらいに来たとのこと。意匠考案からスタートする染匠の仕事にとってなくてはならない大切な工程である。
下絵を描くために参考にするのだろう、たくさんの美術書や専門書籍が並んでるその仕事部屋は「京都の家内職人」の舞台裏、おそらく誰もが知らない世界である。「図案があってそれを元に青花液(注1)で下絵を描くのですか?」の質問に、「今は図案と下絵と両方こなすことが多いです。図案が決まりゆのし(注2)、検尺(注3)を行い、仮絵羽仕立て(注4)を行いその上からやっと下絵です。草案からここまでで結構時間がかかりますよ。」と吉川さん。仕事のやりとりの中でここの職人さんを怒らせ「帰れ!!」と怒鳴られたこともあると当時を振り返る。
「吉川さんはまだまだ伸びはる人。私たちの業界を支えるにあたって大きな力を発揮してくれはるはずやからどうか注目してあげてください」。私たち取材人に投げた職人さんの言葉は紛れもない心の声だと思う。
「きものは私にとってすべてです。もちろん仕事でもあります。自分自身も機会ごとに着ますがやっぱり気恥ずかしさもありますね。でも、きものを着るムードを創る人間が必要だとも考え、市場も確立しておらず開発途中の『男きもの』にアイデンテティを吹き込みたいと思っています。きもの自身なくなることは有り得ません。確かな目と技で作った本物のきものは必ず生き続けていくはずです」。最近、趣味が仕事になってしまった、楽しくて仕方がないと苦笑する吉川さん。若い原動力でどんどん業界を元気づけるとともに、さらなる活躍の場を広げてほしい。一日、本当にお疲れ様でした。
終わり



(注1)青花液とは紫露草(おおぼうしの花)の花のしぼり汁でつくったもの。水溶性で青いインクのような色。
(注2)ゆのしとは生地の長さや幅を整えるために蒸気で生地を伸ばすこと。
(注3)きものの袖、身頃などの部分を割り振りするため長さを計り生地に墨で印をつける。
(注4)きものの形に縫い上げることによって、染め上がりの時に縫い目で柄がずれないように寸法どおり仮縫いする。