|
仕上げの工程で、生地に蒸気をあててシワを伸ばしたり、長
さや幅を揃え、風合いを柔らかくすることを湯のしという。水を使う友禅加工で
は、加工前・中・後など数回にわたって湯のしが行われ、それぞれ下のし、中の
し、上のし(仕上げのし)等と呼ばれる。現在では、テンター(幅出し機)を使った機械湯のしがほとんど。手湯のしは、機械を通すとその特長が失われてしまう恐れのある絞染や刺繍などで使われる。
〈機械湯のし〉
小幅織物の幅出しに使われているテンターは逆ハの字状で、回転する直径60~
70cmの円形の枠に植えられたピンに生地の両耳部分を刺し、蒸気を与えながら幅
を揃えていくピンテンターが多い。生地端を縫い合わせてつなぎ、連続的に加工する。またテンターには、円筒式のほかに、クリップ式がある。
〈手湯のし(手のし)〉
ガスなどの熱源を入れた箱に車を取り付け、銅製の釜を置いた蒸気(ゆげ)発生器と、直径2~3cmで長さ約60cmの木製の丸棒を使う。生地の裏面を外側にして両端を縫い合わせ、輪の状態にし、片一方を枠場の太鼓のような回転する円筒にかけ、もう一方を丸棒に通す。丸棒を両手に持ち、左右に動かしながら釜から出る蒸気の上にかざし、両方の親指で生地の幅を固定しながら丸棒を回転させ、生地の幅を揃えていく。生地の幅は親指の位置によって決まり、丸棒の回転する方向によって幅を縮めたり伸ばしたりできる。 |

手のし |
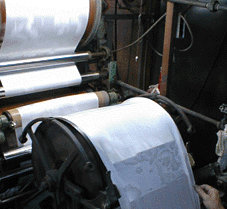
機械のし |
|